
母は浅草の生まれというところから、つねづね江戸っ子であることを自慢にしていたから、戸藉しらべをしてみると、父親は陸中岩谷堂の出身、母親は能登輪島の産というから、とうていサラプレッドの江戸っ子とはいい難い。事実、火鉢を「しばち」などというところはちょっと江戸っ子らしかったが、燕尾服のことを「いんびふく」などというようでは、とても江戸っ子の資格はなさそうであった。要するに、母自身が浅草の生まれで、下町育ちというだけのことにすぎない。
母の話によると、浅草に住んでいたのは、ごく小さい頃のことだというのだが、その小さい頃、浅草界隈で三度も火事に会い、すっかり貧乏になってしまった—ということである。母の生まれは明治四年だから、その時分の浅草の歴史をしらべてみたら、母一家が焼けだされた火事のことも、およそ見当がつくかも知れない。この三度の火事が直接の原因かどうかはわからないが、母自身の語るところによると、「学校がきらいで、三日しか行かなかった」とのことである。しかしこの「三日」というのは、じっさいの三日なのか、それとも「三日坊主」などという、短いあいだを意味する三日なのか判然としない。いずれにせよ、母がろくろく小学校へも通わず、いわゆる「目に一丁字ない」無教育ものだったことは、悲しいながら、私がこの目で見届けて知っている。
西園寺公自伝という本の中に、「原の細君は新橋の下等な芸者で……」とあるが、浅草生まれの無教育ものが、やがて新橋から芸者に出て、西園寺公のお座敷などに出るまでには、この間十年相たち申し候というところだが、この時代のことは、母から聞きもしなかったし、母も語ってはくれなかった。但し、西園寺公のことばとしての「下等な芸者」の一語に関しては、ちょっと註解を加えておく必要がありそうだ。というのは、「下等」というのは、花柳界の格式がC級だったという意味で、けっして西園寺公が芸者としての品性そのものを蔑視していったわけではないことである。
いささか単純すぎるかも知れないが、けっきょく、浅草での三度の火災がもとで、母はそういう境遇に身を置くことになった、と解釈しても、まちがいではなさそうである。こうして妓藉にはいってからの母の行状については、かれこれ耳にしたこともあるが、ここでは割愛さしてもらおう。だが、何はともあれ、これまた「西園寺公自伝」の中の文句を拝借すると、「原の細君になってからは見上げた賢夫人になった」ということになるのだから、母は最大級に面目をほどこしているわけである。
西園寺公が母に感心したについては、こんないきさつがある。それは父の歿後、遺書をひらいたところ、中に、政治献金の残りが数十万円預かってあるが、これは私すべきものではないから次ぎの政友会総裁にひきつぐようにという一項があった。母は父の遺旨にしたがい、西園寺公に一応相談のうえ、無事その金を次代総裁にひきついだ。それだけのことなのだが、これが西園寺公を大そう感服させた。西園寺公にいわせると、「後家さんになると、なかなかあのようにはゆかない。うっかりすると踏みはずすものだが、原の細君は誠にきれいであった」ということになり、母は過分にお褒めのことばを頂載しているのである。浅草生まれの一賢夫人ここにありといったら大袈裟にすぎるであろうか。
【作家・原奎一郎~昭和47年5月号掲載~】
※作品の無断使用を固く禁じます。
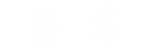










![[お知らせ]浅草活弁祭り2022 浅草東洋館](https://i0.wp.com/gekkan-asakusa.com/wp-content/uploads/2022/09/2022KATSUBEN_MATSURI221029-scaled-1.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1)
