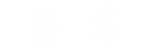ぼくがひんぴんとその街へ出かけたのは、街のすべてが赤裸にむかれた直後のことであった。
その街とは浅草吉野町。一瀬直行さんの寺があった。
空襲のまっさかり、僕は一瀬さんと増上寺で発行している信仰雑誌を編集していたのである。
編集と言っても雑誌は発行されていなかった。計画をねるだけのことである。
地下鉄を浅草駅でくぐり出ると、てくてくと瓦礫の道を歩きはじめる。ぷーんと嫌な匂いが鼻をつく。
死臭だと思った。
三月九日の空襲でおびただしい死者の出たこの界隈だ匂いがまだ街にしみ残っている―と怪奇的に思いこんでいたら、一瀬さんに訂正された。
周囲はカワ屋さんが多い。貯蔵したその皮革が焼けて強烈な匂いを残しているんだそうである。
一瀬さんは、もちろん寺は焼け落ち、新井薬師の方の仮り住居から毎朝寺へ出勤してくる。墓地の石塔にぼんやりと座り込んで一日を暮すのである。檀家の人がやってきて、何やかやと連絡するからだ。
もちろんその場で年回をつとめる法要もやる。
坊空服の上に黒衣一丁をひっかけて、お経を読みはじめる。かたわらには防空頭巾のおばさんがつつましく控えて聴き入っている。
こんな空襲のさなかでも死んだ子の七回忌だけはつとめる寺の息子に生まれながら、良い加減迷っていたぼくは、こんな姿に一つの自信と義務感みたいなものを胸で結んだ。なるほどお寺は、こうした人たちのためにどんなことがあっても守らねばならないんだな、と。
一瀬さんも檀徒が帰って二人で話をはじめると結構アナクロニズムな言葉を口にした。だが、やっていることは立派な坊主であった。
日が落ちるまで墓地でおしゃべりをする。
「同人雑誌、やりたいですねえ」
「ほんとにもりもり小説を書きたいねえ」
一瀬さんも眸を輝かした。
「そうだ。今度の浄土(信仰雑誌)も小説特集にしちゃおうか」
「それもいいですなあ」
どうせ印刷所がテコでも動かず、また割りあての切符だけは貰っても現物化しない用紙。
夢を語っているうちに太陽は六区の彼方、上野の丘に沈んでゆくのであった。
そういえば六区は焼け残っていて、夕方そこをぶらつくと、おびただしい人間が集まっているのに一驚した記憶があった。家を焼かれ、ゆくあてどもない庶民たちはこの街をぶらつき、古くさい映画のハシゴをやっていたのである。
某日熊谷の在へ出かけた帰り道、車中で若い女工員らしい娘さんと親しく口を聞いた。彼女はでっかい革袋を背負っていた。何となく魅かれて彼女の寮がある蒲田まで送っていってやった。
別れぎわに次のデイトの約束をした。六区の大勝館の前で明後日待ち合せることになった。
胸をはずませて出かけたその日、地下鉄が新橋へきたとき空襲警報だ。おろされてしまった。解除まで二時間。こんなに遅刻しては、と諦めてわが家へ戻ってしまった。そうだ。空襲警報で遅刻したのは何も俺一人じゃなかったんだ。彼女だってどこかで・・・と気ずいたのはその晩床へもぐりこんでからであった。
何もなかった。装おいはゼロであった。コーヒーも酒もネオンもなかった。でも浅草はぼくの青春の街と言えたかも知れない。
焼け跡に夏草がおい繁り、赤トンボが群れていたあのころ。
ぼくには現代というものが、いまだに白昼の幻のように思われてならない。
【俳優・寺内大吉~昭和45年6月号掲載~】
※作品の無断使用を固く禁じます。