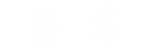東洋興業会長(浅草フランス座演芸場東洋館) 松倉久幸さんの浅草六区芸能伝<第3回>「井上ひさし(いのうえひさし)」
前回は、フランス座の舞台から映画界へと巣立っていった渥美清の物語でしたが、今回はちょうど同じ頃、裏方のほうで活躍してくれていたある文学青年のことを。彼の名は、井上 廈。そう、後に直木賞を受賞し、国民的作家となる井上ひさしです。
当時の劇場の在り方として、役者と物書きとは切っても切れない密接な関係にありました。そのあたりの事情や渥美とのエピソードも含め、お話ししてゆきたいと思います。
昭和31年。オープンから5年を経てなお、フランス座はうなぎ上りの盛況ぶりでした。求人広告ひとつ出しても、応募者が殺到して大行列が出来るほど。
そんな中、難関を突破して入ってきたのが、上智大学仏語科の学生だった井上君です。文章力を買われ文芸部員として採用されたのですが、君は何が得意なのかと聞けば、野球が得意だという(笑)。当時わが社は社会人野球チーム(プロ選手を輩出するほどの強豪だったんですよ)を持っておりましたから、時々練習試合にも駆り出されることになったりしてね。目立つタイプではないものの、なかなかに個性的な青年でした。
ここで少し、彼が配属された文芸部についてご説明しまします。フランス座のショーは、芝居1時間、ストリップ1時間半の二部構成。お客さんはむろんストリップ目当てな訳ですが、踊り子さんが登場するまでの間、芝居でいかに客席を惹きつけるかが、とても重要な要素となります。そこで必要となってくるのが、面白い芝居を書ける小屋専属の脚本家(座付作家)。彼らが籍を置く部署が、文芸部です。作家とはいえ、先生然としていられる訳ではありません。むしろある意味では、下働きのスペシャリストと言えなくもないでしょう(笑)。
まずは、舞台の進行係。幕の上げ下ろしに始まりマイクや小道具の調整、音出し、裏方さんへの指示、出演者の呼び出し、時と場合によっては踊り子さんのお世話から、役者の代行まで!かなり責任の重い大変な仕事ですが、こうして舞台全体の流れを掴んでゆくことが、作品を書く上で何よりの修行となるのです。
そして肝心の台本作りですが、これがまたすこぶるハード!演目は半月ごとに変わるので、15日目は千秋楽でもあり、初日前夜でもあるわけですが、文芸部員は前述の忙しさですから、楽日になってもまだ次のホンが上がってない、なんてことはざらでした。そんな時は全員徹夜で、作家が1頁書くそばから新人がガリ版を切って役者に渡し、稽古をする。文字通りの一夜漬けで初日を迎えるのですから、そりゃ役者も作家も、鍛えられるはずです。舞台裏のドタバタこそ、まさにコメディ(笑)!浅草喜劇人の底力の一端は、こんなところにも起因しているのだろうと思います。
肺結核で療養中だった渥美清がフランス座へ戻ってきたのは、井上君が一生懸命に仕事を覚え、ようやく少し慣れてきた頃のことです。
『噂によると渥美さんという役者は、天才肌の名優だがとんでもない荒くれ者らしい。一体どんな人なのだろう…』と不安交じりに復帰の日を待っていた彼の期待は、良い意味で、ものの見事に裏切られました。噂の役者は生死の堺を彷徨う大病を経て、荒くれ者どころか物静かで品が良く、風格すら感じさせる好人物となっていたからです。その上芝居はといえば、想像を遥かに超える素晴らしさ!井上君はあっという間に、渥美の虜になってしまいました。
そんな思いが通じたのか、渥美の記念すべき復帰第一作には、井上君が採用試験の折りに提出した作品「看護婦の部屋」が選ばれました。脚本の秀逸さと役者の力量が見事にマッチし、舞台は大成功!二人はピッタリと馬が合い、以後、多くの傑作が生まれることとなります。ただ、当時の浅草にはペンロックという物書きの協定があり、所属の脚本家以外の作品を上演してはいけない決まりになっていたので、「作・井上ひさし」と表立って名前を出してやれなかったことが、非常に残念ではあったのですが。
余談になるかもしれませんが、貴重な資料が残っていたので、この場を借りていくつかご紹介したいと思います。