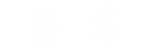劇界の凶年とされる明治10年も秋となり、これからは世の中の景気も立ち直り、芝居は不況を乗り越え、いよいよ繁盛すると皆が喜びはじめたが、10月になって総師格であった五世坂東彦三郎が大阪において46歳の役者盛りで没した。
彦三郎については前にも書いたように容姿音調ともにすぐれ、芸品高い名優であったからその独自の芸風でどの役も器用にこなしたが、なかでも舞台の情調をガラリと変えるその刹那の呼吸が無類で、パッと一変させる眼目の場にもてる芸の力を見事に示し効果をあげた。
その彦三郎の特味・特技に切ってはめたような適役(はまりやく)が、「天一坊」における大岡越前守であり、当時その大岡さまと一対をなした適役の代表が團十郎の水戸黄門であったという。
安宅(あたけ)丸のとりこわし事件を本筋に黄門記の講談から脚色されたお家物、「黄門記童幼講釈(こおもんきおさなごこうしゃく)」、7幕は、明治10年11月、久しぶりに巡業から帰った團十郎を中心にすえた新富座(仮小屋)に黙阿弥が書きおろしたものだ。
>次ページ「團十郎の黄門は、さながらその人を見るが如しと云はれた!」