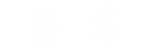<其ノ三~大河内傳次郎(おおこうち でんじろう)騒動~>
名作ミュージカル映画「ウエストサイド物語」に衝撃を受け、矢も楯もたまらず上京を決意した私に周囲は焦り、誰もが馬鹿なことをするなと引き留めた。
彼らの助言も、もっともだ。すでに家庭を持っていたし、なんせ当時は40人もの団員を抱える人気劇団の座長。舞台は連日超満員で、このまま九州を拠点に活動していれば、何不自由ない暮らしが約束されているのだから。
けど、どんなに恵まれた状況にあろうとも、そこで満足はできない。ひとつ夢が叶ったら、またすぐ次の夢を追いかけたくなる。そしていったんこうと決めたら、誰に何と言われようが、自分を信じてまっしぐら!
私のそういう性分は、今も昔も変わらない。また、役者はそうでなければ嘘だと思う。そこを曲げたら、沢竜二は沢竜二でなくなってしまう!
昭和37年、私は単身上京し、のちに女房子供も呼び寄せ、東中野のおんぼろアパートで新生活をスタートさせた。九州ではかなり稼いでいたから、当面の生活には十分な額を持参したつもりでいたのに、やはり東京での生活は厳しい、所持金は半年足らずで底をついてしまった。
その頃の生業は主に、得意の歌を活かしてのキャバレー周り。極貧で、わずか1万3000円の家賃も滞る、食うや食わずの毎日。そんな中でも一つ心に誓っていたのは、どんなに苦労をしても、芸事以外の仕事は決してしないぞ、ということ。
…なんてカッコよく言ってはみても(笑)、現実は待ったなしだ。腹を空かした小さな子供に10円のパンさえ買ってやれない状態には、さすがに困り果ててしまった。〈こんな苦労を掛けるくらいなら、いっそ九州に帰った方がいいのか…?〉日々、気持ちは揺らぐ。
そんな折も折、珍しい来客があった。私に時代劇を基礎から叩き込んでくれた恩師・新国劇の倉橋仙太郎先生だ。
開口一番、先生は言った。
「お前、大河内傳次郎が亡くなったのは、知ってるな?」
「はい、もちろん知ってますが…?」
時代劇の大御所・大河内傳次郎は、倉橋門下の兄弟子に当たる。直接の交流は殆どなかったけれど、芸はもとより漏れ聞こえてくるその人柄にも、常々敬意を抱いていた。
「お前も知っての通り、大河内は俺の一番弟子だ。あれだけの芸が彼の死とともに消えてしまうのは実に忍びないし、奥さんも大変嘆いておられる。誰か然るべき者に、大河内傳次郎の名を継いでもらう訳にはいかないだろうか、と。そこで、ご遺族も含め関係者と話し合った結果、満場一致でお前に白羽の矢が立った。」
「えぇっ⁈」
それはあまりにも意外で、唐突な話だった。私の伺い知れないところで、事態は思わぬ方向に展開していたのだ。
「どうだ?いい話だろう!」
どうだと言いつつ先生の中で、これはすでに決定事項のようだった。そりゃぁそうだ。天下の名優の名を、継がせようというのだ。これで暮らしも楽になる。私がどれほど喜ぶかと思い、駆けつけて下さったのだろう。第一、こんな名誉な話を断る馬鹿な役者など、日本中どこを探したっていやしない(笑)!
…しかし、あろうことかその馬鹿が、私だった。
「先生のお気持ちは本当に有難いし、大河内先生のことも、素晴らしい方だと尊敬しています。そりゃ二代目・大河内傳次郎となれば、間違いなく売れるでしょう。しかし生意気なようですが、人様の築いた名前で売れたとしても、ちっとも嬉しくはありません。あくまでも私は女沢正の倅『沢竜二』として、正々堂々と世に出たいのです。」
数ある門下生の中で、真摯に芸に取り組む私の姿勢を評価し、目をかけてくれた倉橋先生。恩師の期待を裏切る形になってしまったことは本当に申し訳なく、胸の潰れる思いだったが、それでも一番大事な自分の軸だけは、どうしても曲げられなかった。
良くも悪くも、私はそんな生き方しか出来ない男なのだ。
こうして東京での“波乱万丈”な俳優人生は、幕を開けた。
一発目の波もかなり強烈だったけど(笑)、そのうねりも冷めやらぬところへ、赦なく次なる大波が押し寄せて来やがった…!
※掲載写真の無断使用を固く禁じます。