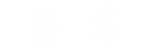気が付けば、季節はもう冬。たけしが浅草へ来てから、半年近くが経っていました。
才能ばかりを取り沙汰されますが、実際のところ、彼は無類の努力家でもあります。人一倍シャイな性格ゆえにその努力を決して表には出しませんが、深見は、そういうところもしっかり見抜いていたのでしょうね。認められるまでに少々時間はかかりましたが、そこから先は、早かった。持てるすべてを注ぎ込んでゆくかのように、深見は次から次へと、自身の芸をたけしに伝授していったのです。
消えかかっている浅草喜劇の灯をともし続けてくれる後継者に、やっと出逢えたと言わんばかりに…。
私生活の面でも、二人は親密さを増してゆきます。フランス座の楽屋に寝泊まりしていたたけしは、師匠と同じアパートの階下に住まうようになり、いつしか連れ立って銭湯や食事へ繰り出すのが日課となりました。たとえば寿司屋へ行っても、深見はほんの少ししか手を付けず、たけしにばかり高級なネタを食べさせます。例のごとく“バカヤロウ、もっと食え!コノヤロウ、遠慮なんかするな!”と毒づきながら、さも嬉しそうに(笑)。その姿はもはや師弟の枠を超え、まるで本当の親子のようでした。
天才肌で芸一途、不器用だけれど情に篤い。気質も性格も本当によく似た二人。公私を共にするように過ごしたこの時期、たけしは師匠のすべてを吸収していたのではないでしょうか。芸人としての在り方や、男として、人としての生き様も。生前の深見を知る者は、一様に口を揃えます。
“たけしは、師匠に生き写しだ”と。
たけしはめきめきと頭角を現し、客席の爆笑を欲しいままにするまでとなりました。時代的に、ストリップ自体がもう衰退の一途を辿っていた頃ですから、客の入りも全盛期とは比べ物にならないほど寂しいものではありましたが、それでもコントのほうを目当てに通ってくれるファンが、少なからず出来たのです。
そうなってくれば、才気溢れる若きコメディアンが更なる上を目指したくなるのは、ごく自然の成り行き。たけしにもまた、フランス座を出て外の世界で自らの実力を試してみたいという気持ちが芽生え、その熱い思いは、日ごとに大きく膨らんでいったのです。
しかし、一番の気がかりは、もはや親父同然の存在になっている、深見師匠のこと。今までも数えきれないほどの弟子を持ち、世に送り出している師匠にしてみれば、いつかは別れの日が来ることを、想定してはいるだろう。けれど、自分が他の弟子たちとは比べ物にならないほど可愛がられ、期待されていることは、痛いくらいに解かっている。その期待を裏切るようなかたちになってしまったら、師匠はどれほど傷つくことだろう…。
けれど、どんなに師匠を想ってはいても、一度抱いてしまった情熱を、もはや抑える術などないのでした。
そんなたけしに、二人で漫才をやってみないかと誘いをかけてきたのが、同僚の兼子二郎(のちのビートきよし)です。山形県出身で、芸人としてはたけしよりも二つ先輩。ロック座時代から深見のもとでみっちりと鍛え上げられた、なかなか根性のある男でした。“テレビに出るまでは、決して故郷に帰らない”と宣言して上京してからはや数年。彼もまた、ここを飛び出し、一日も早く世に出たいとの思いを募らせていたのです。
たけしは当初、兼子の誘いに全く乗り気ではありませんでした。深見が、常日頃から“漫才なんて芸とは認めない”と、口を酸っぱくして言っていたからです。
どのみち師匠を傷つけてここを出てゆくことになるのなら、せめて師匠から受け継いだ芸で世に出たい。もっともっと腕を磨いて、コントで勝負するんだ、と。
そう心を決めたたけしは、息の合った後輩を相方に定め、舞台が跳ねるとフランス座の屋上に立ち、来る日も来る日もコントの練習に明け暮れました。ところが、何という運命のいたずらでしょう、大切な相方が、再起不能なほどの重い病に倒れてしまったのです…!
松倉久幸(浅草演芸ホール)
(口述筆記:高橋まい子)
※掲載写真の無断使用を固く禁じます。