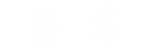東京の人間は、浅草を〝郷愁の町〟という。だが、私のように、東京にあこがれて家で同様にして上京してきた人間(こんな人間は今も多いだろう)にとっても、浅草は、同じように、いや、それ以上に 〝郷愁の町〟 なのである。
私の場合をいえば、浅草は、銀座なんかより、ずっとずっとアコガレの町であった。
それは、高見順の、川端康成の、永井荷風の、久保田万太郎の、サトウハチローの、あるいはまた樋口一葉の、安藤鶴雄の町だった。それらの文士や詩人たちが描いたその町のたたずまいを、私は、郷愁の山河よりも親しいもののように胸に抱いたものだ。
はじめて浅草の灯を見たのが昭和十六年。もう三十年も昔のことになるのだから、全く月日の経つのは早いものだ。
大陸から復員してきて、また東京に舞い戻った私は、職を得て東京に住みつくことになったが、浅草には住まなかった。
世田谷、杉並などのサラリーマン住宅地に住み、銀座の新聞社に通った。まず、浅草とは縁遠い生活環境の中で二十何年か過した。
が、そのわりには、私はせっせと浅草に通ったほうだろう。
同僚と銀座のバーを飲み歩いていて、一人で浅草へタクシーを飛ばしたことも何度かあった。一人でふらっとはいったふぐ屋でストリッパーと仲よくなって、それからしばらくつきあったこともあった。
四十歳近くなって、国際劇場のレビューに魅せられて通ったこともあった。
今はなくなったけれども瓢箪池のそばで、酔っぱらって喧嘩をしたこともあった。
野一色さんが世話をしていらっしゃるお酉様の会も毎年楽しみにして欠かさず通った。
それやこれや浅草との因縁はいくつかある。
つい先だっての三月十日、陸軍記念に、加太こうじさんや阿部進さん、加藤尚文さんらといっしょに、文化放送の人の肝いりで、「軍歌を歌う会」を花月食堂でやった。どうせのことだから、民族衣装で勢揃いしようや、という話になって、ぞろりと着物なんかを着て出かけ、大いに愉快に酔っ払った。
加太さんがさまざまな仁義の切り方を見せて下さったりして楽しかったが、ちょっと残念だったのは、夜の七時だというのに、すこし雨が降り出したと思ったら、仲見世の店がどんどん戸を閉め始めたことだ。
これじゃァ、客は来なくなるのも無理はない、と思って、一軒の店の主人に声をかけたら、
「なに、商売になるんだったら私たちだっていつまででも開けていたいですよ。だけど、どうせ客は来ないんだから。」
なんだかヤケクソとも聞える話しっぷりだった。
客が来ないから、店を早く閉めちまうのか、店がすぐ閉まっちゃうから、客足も遠のくのか、鶏が先か、卵が先か、みたいな話で、私などには判断のしようもないが、春の雨がしょぼしょぼと降り出した仲見世で早仕舞いする店の気配を聞くのは、なんともいえず淋しかった。
が、その淋しいところが、またなんとなく風情があってなんて思っているのだから世話はない。「浅草を叱る」なんて題を貰ったけれども、私には、浅草を叱ることなんてできそうもない。
【評論家・塩田丸男~昭和45年6月号掲載~】
※作品の転載を固く禁じます。