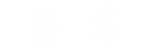七段目の「お軽」を扱った小唄をひとつ。
〽吊灯篭の明かりに照らし、読む長文を二階から、余所の恋よと延鏡、かざすはずみに顔と顔
間男があるなら添わしてやろうせめて三日と手を取って、九ツ梯子かるがると
身請けされるが嬉しさに心は飛んで山崎へ
一筆しめし参らせる

これは、由良之助に三日なりとも囲ったらそれからは勝手次第といわれ故郷に帰れる嬉しさに、山崎の父・母・勘平にこの思いがけぬ身請話しを知らせる手紙を書き始めるところで、前段は、はでに色っぽく廓情緒を出して唄い、〽身請けされるが嬉しさに、から、身請けして刺し殺さんという由良之助の心を知らず、浮々と便りを書くお軽の哀れな後ろ姿を唄うようにという。
さて、舞台だが二階のお軽、中段に由良之助、下段の縁の下の九太夫という、三人の絵模様の趣向はおもしろい。
この分を読むところ、九世團十郎は垂らして読む彦三郎の形があまりにも色気があって無類、とてもあの真似は出来ないと右に巻きながら読む型に逃げたとか。
近年では、初世吉右衛門が、初世鴈治郎のを見物して「もう七段目だけはやりたくな」と自信をなくしたなどという逸話が残っている。
お軽のかんざしがぱったりと落ちたことから、由良之助はそれに気付いて、両人の対話となる。
「由良さんか」
「お軽か、そもじはそこに何してぞ」
「わたしゃおまえに、盛りつぶされ、あんまりつらさに酔(えひ)ざまし、風にふかれて居るわいなア」

お軽は〝はや里なれた〟なまめかしい姿だ。
秘密を知ったお軽をほかへ逃がすまいと、あり合せた九ツ梯子を持ち出してお軽を二階からうまくおろすことになる。そして〝ぢやらつき出し〟て身請の相談となる。「間夫(まぶ)があるなら、添わしてやる」というのでお軽は夢かと喜ぶが、由良之助の心底は、手紙を読まれた女、請出して刺殺すつもりである。
由良之助が身請に奥へ入ると独吟となる。
〽世にも因果な者なら我(わし)が身じゃ
可愛い男に幾代の思い、エゝ、
なんじゃいな、おかしゃんせ、
忍ぶ音に泣く小夜千鳥。
〽奥でうたうも身の上と、お軽は、試案とりどりに
お軽が座敷に上り、手紙を書ているところへ。
〽折から出てくる平右衛門…
と、にぎやかな騒ぎの三味線となり、妹のお軽を探しながら、平右衛門の出となる。
久しぶりの体面に兄妹は喜び合うが、平右衛門は妹から身請けと手紙の件を聞いて、すぐに事情を悟る。
平右衛門は秘密を知ったお軽を殺そうという由良之助の苦慮を考え、その手をわずらわすまでもなく、自分が手にかけ、それを手柄に連判に加えてもらおうと、心に極めお軽を呼び寄せ
「妹、われが命は兄がもらった」
といきなり切りかゝる。
驚いて逃げまどいながら許しを請うお軽。
平右衛門はこゝで初めて与市兵衛と勘平の非業の死を打ちける。
「神の飾りに化粧(けわい)して、その日その日は送れども、可愛や妹、わりゃなんにも知らねぇな……」
お軽が身も世もあらず悲しんだことはいうまでもない。兄も妹の心を察し、手を取り合って涙にくれた。

「勿体ないが父(とと)さんは、非業な死でもお年の上、勘平さんは三十に
〽なるやならずに死ぬるとは「さぞ、悲しかろ、口惜しかろ」「逢いたかったであろうなァ」「アイ」
〽なぜ逢しては下さんせぬ。「親・夫の精進さえ、知らぬわたしが身の因果、なんの生きていられましょう…」
やがて気を静めたお軽は覚悟を決め、平右衛門のため死ぬことを承知する…
この時、由良之助が手ち出て、両人の誠を認め、平右衛門の連番の一味加盟を許し、お軽には縁の下の九太夫を刺させ、勘平の代りに手柄を立てさせる。
由良之助というのは、いつも感情を表に出さず肘で物事を運びながら、それでいて終始舞台を引き締めてゆかねばならず、歴代の座頭役者が工夫をこらしつゝ、なお満足が出来なかったという、歌舞伎諸役中、頂点にたつ大変な役である。
こゝに、七段目の面白い川柳をいくつか選んでみました。
◆由良鬼はいくら酔っても正気也
◆乳繰ったむくひでお軽祇園町
◆国家老鮒の逮夜に蛸を食ひ
◆足を食ひ其手は食はぬ由良之助
◆計略で置く魂は真赤なり
◆喰はせたり喰ったり蛸と赤鰯
◆売られてもお軽やっぱりお軽也
◆縁の下老眼でなほははかどらず
◆お年の上などとお軽も不孝者
◆蛸の意趣鰯ではらす心地よさ