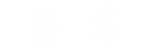浅草といえば観音さま。観音さまというと鳩の豆売りのおばあさんが思われる。下町育ちのわたしの古いアルバムには観音さまの境内で鳩に豆をやっている写真がある。たぶん二歳くらいだろう。赤と思える麻の葉模様のしぼりのきものを着て、ちゃんちゃんこをかさねその上に裾まで届く白いエプロンをつけている。頭には正ちゃん帽をかぶっていて、まぎれもない大正風俗だ。
鳩が一羽餌をついばんでいるが、背景に豆売りの屋台が写り、これにつきものの和傘が拡がっていて、おばあさんがシルエットになって坐っている姿がある。溜息の出るほど懐かしい。
写真ではよくわからないが屋台の上にブリキの皿が並べられ、その上に売り物の豆がのせられているのだ。一皿一銭だったか、二皿一銭だったか、その辺になると覚えがない。皺だらけの手でブリキの皿を渡してくれる。豆を撒こうとすると、もうまわりに鳩が集まり、チビのわたしは泣きべそをかくのだった。
この写真の他にもう一枚並んで貼ってあるのは仲店の人ごみをいくわたしと母。廂髪にあげ、刺繍の半衿をたっぷり出して地味なきものを着ているが、二十四、五歳のはずである。母はその後離婚してわたしを捨てて去るのだから、これは豆売りのおばあさんの姿とともに母子の数少ない貴重な写真である。
小学生のころは祖父母に育てられて、そのお供でチョイチョイ観音に詣でた。必ず内陣にあがり、薄暗い場所をめぐり、長い祈りをじっと待っていなければならない。外へ出ても淡島様、浅草神社、弁天さま、粂の平内さまとあっちこっちにお詣りするので閉口だった。その代り帰りがけには弁天山の鮨やでおいしいずけを食べさせてもらえるのでごきげんである。
ところがこのコースが狂ったことがあった。わたしを供にしたまま祖父は吉原の大門をくぐったのである。そしてもう写真見世になっていた妓楼を一軒一軒のぞいて歩いたのだ。いっしょにおいらんの写真を眺めたけれど、じきにあきてしまった。そしてしーんとした妓楼の大きな建物が無気味で、早く家に帰りたくなり、何度も祖父の袂をひっぱって催促をした。
結婚してからも初詣りはもちろん、なにかというとすぐ観音さまに足がむく。昭和三十八年の夏本堂で何げなくひいたおみくじが何と大吉で「枯木に花」とあった。この卦がわたしの転機になった。その数日後に「週刊朝日」の終戦の手記に特選入賞し、以後ものかきの道を歩き出すからである。もう四十歳で枯木寸前だったわたしが思いかけなく花を咲かせ、ノンフィクションライターとして仕事にいどみ、生まれ変ったように働き出したのだ。このときかぎりわたしはどんなおみくじもひくのがこわくなった。
いまも浅草に出かけると別世界がセリ上ってくるような気がする。仲店の敷石を踏みしめながら本堂までたどり、お詣りをしたあと必ず淡島さまに寄り、六角堂を眺めるのも幼い日の習慣通りをなぞっている。ただ違うのは、レストランアリゾナをのぞき、それから吾妻橋の上に立つことだろう。
これはいわずと知れた永井荷風の晩年を偲んでのことである。荷風は終戦後市川で独り暮らしをしていたが、毎日買物袋を下げ下駄ばきという姿で京成電車で浅草に通った。観音の境内のベンチでぼんやり物思いにふけり、アリゾナで食事をし、吾妻橋に立って対岸の朝日ビールの建物や川面をあきることなくのぞく。
わたしも同じことをしてみる。してみたからといって荷風のような名作が書けるわけではない。ときには隅田公園を抜けて待乳山まで足をのばす。これも荷風の「すみだ川」の世界をうろつくためである。明治のみならず大正も遠くなった。しかし浅草ある限りわたしの望郷の思いはいつか充たされるのである。
【作家・近藤富枝】
※作品の転載を固く禁じます。