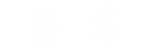〜師匠から託されたメッセージ〜
夏のある日、浅草木馬亭の前に15人ほどの列ができていた。毎月中旬に行われるお笑いの劇団「浅草21世紀」の公演である。お客さんはややご年配が多い印象。入り口では、劇団員さんが後期高齢医療制度について軽口をたたいて、炎天下に並ぶお客さんたちを楽しませていた。開演前からお客さんを笑わせる喜劇役者ならではの歓迎だ。
浅草21世紀は、浅草から国民的コメディアンを輩出するために、橋達也と青空球児が1998年に旗揚げした劇団だ。浅草喜劇の伝統を継承する一翼を担っている。初代座長は橋達也、副座長には青空球児と関敬六が就任した。関敬六は、偉大なコメディアンであるとともに、渥美清の無二の親友として知られる人物だ。
前置きが長くなったが、関敬六にはたった1人の弟子がいた。それが関遊六だ。敬六の弟子になりたくて、ひとまず付き人になった彼は、野心家ではなかったから、敬六の近くにいられるだけで幸せだった。送迎、身の回りのお世話、舞台の裏方スタッフ、街頭での呼び込み…と、敬六のためなら喜んでこなした。しかし、そんな姿が敬六の目には平凡に映ったのかもしれない。芸人としての才能の片鱗を感じられなかった。遂に敬六は話を切り出した。「坊や(遊六)は芸人に向いていないよ。堅気になって田舎へ戻った方がいい。無理なんだ。ごめんな…」。師匠にここまで言わせてしまった。ここで諦めないと失礼だなと思った。「…わかりました。でも最後に、あと1週間だけついて回っていいですか?」彼なりに気持ちの整理をしたかったのかもしれない。遊六はすがりついた。
関敬六には、小岩で経営するスナック店があった。当然、付き人だった遊六もお店の手伝いをしていた。お客さんからリクエストを聞き、カラオケの機械にレーザーディスクを入れて再生する。あとはひたすらお客さんの歌を聴くだけだ。「師匠の近くにいられるのは泣いても笑ってもあと1週間。もう怒られてもいい。思いっきり楽しんでやろう!」。遊六の中の何かが吹っ切れた。突然狂ったように踊り出し、お客さんのマイクを奪って歌い出す。勝手口の近くの部屋に衣装がたくさん置いてあったから、それを引っ張り出して次々とモノマネを始めた。それを見ていた敬六の芸人魂にも火がついて、「(瞼の母の)忠太郎役は俺がやる!」と言い出して衣装を着替えて飛び出した。「じゃあ、俺がお浜(忠太郎の母)をやりますね!」突如として、敬六と遊六の即興喜劇が始まった。帰り道、敬六はしばらく黙っていたが、ふいに口を開いて言った。「君、面白いね」。関敬六から初めて芸人としての可能性を見出された瞬間だった。
遊六の初舞台は突然やってきた。5〜6人で行われるコントに出演予定だった三木のり平が急遽来られなくなった時、座長から「お前が出ろ」と指名された。敬六からは、「舞台の怖さを知れ」と言われた。その言葉通りで、もはや初舞台の記憶はない。それから、敬六の前説を任されるようになった。1分程度の前説だったが、毎回新しいネタを考え、師匠の家に行って見てもらった。深夜の訪問でも温かく奥さんが出迎えてくれて、いつも敬六はリビングでテレビを見ていた。
遊六は、敬六が亡くなる直前まで自宅や病院へ足繁く通った。敬六が亡くなり葬儀が終わった時、座長の橋達也のところへ行くと、遊六が口を開けるよりも前に「お前は辞めなくていいからな。関さんから頼まれてるんだから。気にするな」と言われた。そう、遊六は劇団をやめるつもりだったのだ。そんな遊六を見透かして生前のうちに手を回してくれていた関敬六。最後の最後まで愛情深い師匠だった。
1度は「芸人には向いていないから辞めなさい」と見放された遊六が、最後は「お前は芸人として生きていけ」というメッセージを託された。あのスナック店での土壇場の状況で、とんでもないエネルギーを放って破茶滅茶をやってのけた遊六のパワーを信じていたのだろう。これからも、舞台上で一心不乱に爆発する姿を期待したい。

今回書ききれなかった面白エピソードは、YouTubeチャンネル「浅草ユーチューブ!月刊浅草ウェブ」で紹介しています。併せてお楽しみください。
【information】
令和4年9月の「浅草21世紀」公演は、9月11日〜18日。場所は浅草木馬亭。チケットは前売り2300円。ウェブサイトは、asakusa21.com お問合せは、03-3844-2130。
どうぞ皆さまお誘い合わせの上、お気軽にご来場くださいませ!
(月刊浅草・令和4年9月号掲載)
【筆者紹介】
活弁士・麻生子八咫(あそうこやた):父麻生八咫に弟子入りし、10歳の時に浅草木馬亭で活弁士としてデビュー。
活弁は、サイレント映画に語りをつけるライブパフォーマンスです。どうぞよろしくお願いします。
※写真の転載を固く禁じます。