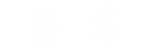東洋興業会長(浅草フランス座演芸場東洋館) 松倉久幸さんの浅草六区芸能伝<第9回>「浅草演芸ホール誕生秘話」
ここまでは、渥美清に始まり先月号のコント55号まで、主にフランス座と東洋劇場で活躍したコメディアンたちのことを中心にお伝えしてまいりましたが、今回はちょっと趣を変えて、落語のお話などいかがでしょう?
昭和39年に二度目の大きな方向転換をはかり、寄席を新設することになった東洋興業ですが、そこへ至るには、運命的ともいえるとても面白いエピソードがありました。そして、あまり知られていないことですが、我らが台東区と落語との深い縁についても、これを機会にぜひ知ってただきたいと思います。
時は昭和30年代後半、浅草六区興行街はまたもやピンチに立たされていました。昭和39年に開催される東京オリンピックに向けて体裁を整えようという政府の方針により、ストリップに対する取り締まりが強化されたため、経営困難に陥る小屋が続出したのです。勿論わが社とて、例外ではありません。何とかしてこの状況を乗り切るべく、早急な対策をとる必要に迫られました。でも、どうやって?…そんな折、まるで笑いの神様がどこかで見ていて助け船を出してくれたかのように、思わぬ話が舞い込んだのです。
当時、文京区弥生町に「弥生ハウス」という小さなアパートがありました。どういうわけか芸人が多く住んでおり、通称“芸人村”とも呼ばれていたらしい。うちの文芸部員の高崎三郎が、このアパートの住人でした。
ある日、たまたま隣室に住んでいた落語家・桂枝太郎が、高崎にこんな話を持ち掛けたのです。
「浅草には今、寄席が一軒もありませんよね。東洋興業さんは、同じ建物内のフランス座と東洋劇場で、どちらもストリップと軽劇の二本立てという同じようなショーをやっていらっしゃる。どうです、ここはひとつ思い切って、どちらかの劇場を寄席にしてみるというのは?」
突拍子もない案だとは思いましたが、高崎は一応、この件を会社で話してみました。すると、どうでしょう。ちょうど改革の方向性について思いあぐねていた経営陣は、これは渡りに船とばかりに、彼の提案を大乗り気で受け入れたのです。きっかけは、アパートの住人同士の何気ない立ち話。まったく世の中、何がご縁になるかわからないものですね(笑)。
浅草にはかつて、浅草末廣亭という寄席がありました。戦後まもなく誕生したその小屋は、残念ながら定着せず、わずか一年あまりで姿を消しています。そういういきさつもあるので、果たして今またこの街に、落語は受け入れられるのだろうか…という一抹の不安もありましたが、足踏みしている場合ではありません。
この苦境を逆手に取り、“浅草に寄席を復活させよう!”という目標を掲げ、社員一丸となって新たなる挑戦へと漕ぎ出したのです。