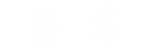それからのたけしと兼子は、相当苦労を重ねたようです。フランス座のギャラだって雀の涙ほどだったけれど、まさかそれ以上の貧乏を経験することになろうとは、思いもよらなかったでしょう。あまりに腹が減って、浅草寺の鳩まで喰っちゃったなんてネタも、あながち嘘ではなかったかも知れませんね(笑)。
客が一人の劇場でも前座をこなし、キャバレーの営業で食いつなぎ、必死で試行錯誤を繰り返しながら、徐々に実力を身につけてゆきました。たけしがどんなハチャメチャをしても否定せず、自由にやらせて受け止めた兼子の度量も、素晴らしかったと思います。こうして築き上げた独自のスタイル、従来の概念を覆すほど斬新な漫才は、賛否両論巻き起こしつつも次第に注目を集め出し、あれよあれよという間に二人は、時代の寵児となってゆきました。
コンビ名あらため、「ツービート」。ビートたけし・ビートきよしは、こうして世に送り出されたのです。
紆余曲折あったものの、どんな形であれ愛弟子のたけしは超売れっ子の大スターとなり、漫才ブームが過ぎ去った後にもその豊かすぎる才能を見事に開花させたのですから、深見はどんなにか嬉しかったことでしょう。一時は断絶してしまったかに見えた師弟の絆も、時を経て雪解けを迎え、いつのころからかまた浅草の街では、多忙なスケジュールの合間を縫っては師匠に会いに来るたけしの姿が、見られるようになったのです。
しかし二度目の別れは、ある日突然に訪れました。
昭和58年の真冬の夜、独り住まいのアパートで寝たばこをふかしていたらしい深見は、火の不始末から小火を出し、あっけなく還らぬ人となってしまったのです。
たけしの受けた衝撃は、如何ばかりだったことか。いつかは師匠の芸を越えたかった、これからもっともっと“親孝行”したかった…さまざまな想いが去来し、胸を締め付けたことでしょう。しかし、深見にとってせめてもの救いは、“最愛の息子”と酒を酌み交わす日が再び訪れていたこと、そして何より、たけしがこんなに立派に出世したことに他なりません。
たけしにとっては、永遠に超えられない存在となってしまった師匠。けれど、深見の中では、もうとっくにたけしは、自分を越えていたのではないでしょうか。最後にして最高の弟子を育てることが出来て、彼はきっと満足していたはずです。なぜって、たけしのことをちょっぴり自慢げに話すときの彼は、本当によい顔をしていましたから。
波乱万丈の人生、哀しい最期ではありましたが、間違いなく彼は、幸せだったと思うのです。殊に、たけしと過ごした晩年の日々は…。
『浅草喜劇の灯は、深見とともに消えた。』『いや、たけしこそが、最後の浅草芸人だ。』時として、そんな言葉を耳にします。果たして“最後の浅草芸人”は、深見なのか、たけしなのか…?
私は敢えて、『どちらでもない。』と、断言しましょう。浅草喜劇の灯は、消えてなどいません。今もなお、明日のスターを夢見て懸命に修行している若者たちの心に、熱く灯り続けているのです。
渥美清、三波伸介、東八郎、萩本欽一、そして、ビートたけし。浅草フランス座演芸場東洋館のショウウインドーには、わが劇場から巣立っていった錚々たる芸人たちの顔写真がピンナップされています。彼らに追随する天才芸人がいつの日かまた、ここから誕生しますようにとの、切なる願いを込めて。この街に、“最後”などという後ろ向きな言葉は、似合わない。浅草六区ブロードウェイはいつだって、未来へと繋がっているのですから!
松倉久幸(浅草演芸ホール)
(口述筆記:高橋まい子)
※掲載写真の無断使用を固く禁じます。