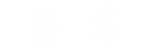狭い町なみの廂間(ひあわい)から十二階凌雲閣がうす墨いろに見えていたが、初夏の日長の暮色はまだ明るく、それらしい町なみへはいって行ったが、ひっそりとしていて声をかけてくる者もない。時間が早いからであろうと路次をぬけで観音さまの境内へいき時間をかせぎ、再び銘酒屋へいくと、そこここで呼ぶ声がした。「ちょいと書生さん」「ハカマの旦那」など。夜学通いから道をそれてきたので、ハンチング、紺がすりに小倉の袴、朴歯の下駄、本包みをかかえていたのであった。
呼ばれるたびに、強引に引っぱりこんでくれないかと期待し、そのくせ、胸がドキドキして足早になった二筋、三筋まわるうちに、せっかく冒険に来て、手を空しゅうて帰っては経験にならないと、当時の文学青年の経験尊重の観念が、むくむくと頭をもたげて勇を鼓して一軒の土間に入って行った。
入ったところは狭い土間で、上り口に障子がしまっていて、その障子の目どおりにガラスがはまっている。ガラスごしにのぞいて見た。
三、四人の女がいた。その中のひとりが清方えがく女のように記憶に烙きついている。樋口一葉の作中の女のイメージが揺曳していたようである。
その女は清方えがくから寺島紫明になり、年月とともに変わっていき、五十年後には、「墨東奇譚」の山本富士子へうつっていき、昇華された影をとどめているにすぎなかった。
強引に引っぱってくれたら…という期待は外れて市電の停留所へ、十円と童貞は無事ですんだ。が、あのとき、強引に引っぱり上げられていたら…わたしの人生はもっとちがった途をたどっていたか知れなかった。初めて女を知ったということ。不幸にして(?)清方えがく女のような女にめぐり合ったとすれば…盲滅法の人生へ踏みこんで行ったか知れなかった…
往時ぼうぼう…わたしは筆をとって
伝法院の若葉の雨となりにけり
上五を「浅草の寺」と初案(しょあん)したが、焦点がぼやけるとおもい、且つ伝法院の庭を散策した日のことをおもい合わせ、一隅をあげて全豹を示すことになれば…とおもったことだった。
〈完〉
(昭和45年7月号掲載)