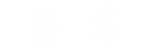鐘の音で目をさました。まだもうろうとしている頭の中のとこかで、ここはどこだろう、わたしが八年間いまもやっかいになっているお寺に鐘楼はない、本堂の軒さきに火の見やぐらの半鐘めく鐘がつってあって、撞木槌がセロテープでぶらさげてあって…年にいちどお会式の萬燈ふりの日、かんかんと打鳴らされる。がそれは出火の半鐘の音であって鐘の音ではない…いま聞えている鐘は…あゝそうだ…ここは浅草寺境内に近い…ゆうべ、わたしはここに泊まったのだ…浅草寺の鐘だろうか…わたしは数年以前から毎月朔日…おつきあいで観音さまにお参りしていた。いまも都合つき次第お朔日にお参りしているが…鐘楼、鐘がどこにあるのか…知らないでいる。伝法院にあったか知ら…もうろうと、とりとめもない目覚めであった。
窓のカーテンをあけると、すぐ目の前に若菜の銀杏の大樹の枝々が、大空にむかってのび上がっているように見える。ゆうべ、ホステスさんがおいて行った色紙が机にある。芭蕉の「花の雲鐘は上野か浅草か」正風確立後の芭蕉にしては気取り、気負いの見える句だが…そんなことをおもうのだった。泊まりの紹介者が釣り仲間で宿のあるじは色紙の用意をしてくれたのであった。どこへ行っても、でたらめの住所姓名を書くことはせぬくせもあって、ときに気がすすまず、いやになることもあるが、これも小説などを書いて(今はいたとするべきか)得た虚名の税金か、罰かと悪筆悪句で、色紙短冊をよごすことがある。
ぼうぼう半世紀五十余年、浅草で思いだすのは十二階下の銘酒屋で、わたしは某先生の玄関番書生で二十歳。萬朝報の懸賞小説で得た金十円をふところにすると、かねて空想していた十二階下へ出かけた。夜学へいくふりをして市電に乗り、渋谷から浅草までの途中、どんなことをおもい考えていたのか、いまは何の記憶もない。おそらく初陣の若武者かなにかのようにそわそわわくわくしていたのだ。
市電が往復九銭、そばのもりかけ三銭、銀座カフェ・パウリスタのコーヒー五銭、総合雑誌「太陽」三十銭、婦人世界十五銭。そんな時代の十円で銘酒屋でどんなあそびをしようとしたのか。あそび代はいくらであるのか、わたしは知らないで出かけたのであった。
〈後編へつづく〉
(昭和45年7月号掲載)