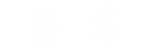私は子供のころ道灌山の東がわ、日暮里村の村外れに近いあたりに住んでいたので、道灌山へのぼるといつでも東南の南寄りのほうに浅草の十二階が見えた。そのころは三河島村から入谷あたりまでずっと田圃つづきで、高い建物などは一つもなかったからだ。
父親にはじめて浅草へ連れて行かれたのは小学校へあがる前で、上野山下までは電車がきていたが、そこから浅草まではまだ鉄道馬車だった。上野までは汽車に乗ったのである。浅草では花屋敷へ入って操つり人形などを見て、広小路の牛屋で飯を食って帰ってきたようだ。
小学校へ行くようになってからは、近所の悪童たちといっしょによく歩いて浅草へ出かけた。音無川に御行の松へ出て、入谷をぬけて公園に出るのだが、一里半ぐらいはあったのではないかと思う。小遣を十銭もらって、五銭あれば活動写真が見られた。
公園には活動写真館、芝居、寄席、そういった興行物が軒をならべていて、飲食店も多く、すべてが格安で庶民的だから、明治、大正、昭和にかけて東京中の唯一の遊び場だった観がある。
大正の初期、私が中学校の二年生だったころ、Sという同級生から学校の帰りに、浅草へ行かぬかとさそわれたことがある。学校の帰りに浅草へまわるなどということは不良少年のすることで、学校に知られるとそれこそ大問題になる。それを承知で彼のさそいに応じたほど、浅草は私にとって魅力があった。彼は私を連れてまず鮨屋横丁へ行って腹をこしらえ、それから五一郎一座の喜劇を見た。その後も毎週一度か二度かは、必ず私をさそう。そして必ず鮨屋横丁から五一郎一座を見に行く。金主は無論いつも彼なので、おまえよくそんなに金があるなあと私が聞くと、彼は水戸の米問屋の二男か三男で、なあに、金は帰省している間にくすねて、着物の衿に縫い込んで持ってくるのさといって、わらっていた。そんなくらいだから、相当不良っ気はあったようだが、幸いそのうちにどこかへ転校してしまったので、私は彼から鮨屋と五一郎一座を見る以上の誘惑をうけずにすんだ。
私は社会人になってからも、娯楽を求めてよく浅草へ出かけた。映画、芝居、歌劇、娘義太夫から安来節まで、私にそういういろいろな庶民の芸能をたのしませてくれたのは浅草である。安来節がはやったのは大正十二年の関東大震災があった後で、この大震災の時、私は浅草の焼けるのを道灌山から見ていた。夜になって大火が天を焦し、半円を描いてめらめらとこっちへ迫ってくるような眺めは、この世のものとは思えぬ恐怖のうちにも壮絶さがあった。
ようやく火がおさまった時は、十二階の頭が欠け、瓢箪池には一杯死骸が浮いていると聞いたが、私にはとてもそれを見に行く勇気はなかった。
そのころ今戸に友人の画家がいて、いつも浅草がよいの私のよき相棒だったが、彼は一家をつれて茨城のほうへ無事に非難しているとわかった時は、実にうれしかった。
それにしても、あの時の浅草の復興ぶりは目ざましいものがあって、あの郷土色ゆたかでいさましい安来節が大当たりをとり、まだ灰色だった東京に一脈の活気を添えてくれたことは、今考えてもなるほどとうなずけるような気がする。
とにかく、浅草は私にとって子供の時から娯楽のふるさとではあったが、その浅草を思い出す時、なぜかいつも懐かしく耳についてくるのは、あの哀調をおびた仲見世の大正琴であり、そのころはただなんとなく見すごしてきた瓢箪池のたたずまいである。その二つとも今はない。
【作家・山手樹一郎~昭和46年新年号掲載~】
※作品の無断使用を固く禁じます。