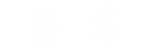吉原のある日つゆけき蜻蛉かな
浅草にうつりて蚊帳のわかれかな
万太郎先生と浅草とは切っても切れない。明治22年(1988年)浅草区田原町3丁目で生まれた万太郎は、大正3年5月に同区駒形に移り住んだ。大正7年隣家から火事が出て、ほとんど着のみ着のままで焼け出されて、こんどは三筋町に居を移した。12年の大震災に遭い、34年間の浅草生活と訣別して、あとは日暮里渡辺町、昭和にはいってからは、芝区三田、敗戦後は鎌倉に10年、東京に戻って湯島天神下、赤坂に住み、昭和38年没した。
おそらく生涯、浅草は万太郎にとって、忘れがたい土地であったろう。たんに生ぶ湯を使ってから34年間住んだという物理的な理由からだけではない。文豪久保田万太郎の人と芸術は、浅草を切りはなしては語れないのだ。生っ粋の江戸っ子……そのいい面も悪い面もかねそなえた人であったが、処女作の「朝顔」や名作「末枯」をはじめ、絶唱と呼ばれる名句の数々はそのほとんどが、浅草を舞台にしている。
冒頭の二句は、いまも愛誦される名句。第一旬の季語は蜻蛉で秋……つゆ(露)けきは、吉原を表現した言葉。秋も深まって、なんとなく街全体が露っぽく感じられるある日、とんぼが群れとんでいるのが見られた。第二句は蚊帳のわかれが季語でこれも秋季……ふつう蚊帳といえば夏だが、わかれとつくと秋となる。
万太郎が樋ロ一葉の「丈くらべ」の全文を暗誦していて、学生にその講義をするとき、吉原の話を3時間立てつづけにしゃべったということをきいて、舌を捲いたが、一葉にいかに心酔していたか、また浅草とくに吉原にいかに深い愛着をいだいていたか、うかがわせるエピソードである。もちろん、万太郎はある時期には、芝居好き、寄席好き、廓好きの手のつけられない蕩児であった。
吉原のみよりいまなき祭かな
三昧線をはなせば眠しほととぎす
海蠃(ばい)の子の廓ともりてわかれけり
竹馬やいろはにほへとちりぢりに
祭(夏)、ほととぎす(夏)、ばい(秋)、竹馬(冬)がそれぞれの季語で、第二句には「女いる—吉原にて—」という前書がふされている。ばいはべい独楽(ごま)のことで、べい独楽に打ち興じていた廊のなかに住む子どもたちが、ともりて灯ともしごろともなれば、わかれてそれぞれの家に帰ってゆく。次の竹馬の句もおなじような情景で、哀愁をつよく打ち出している。現実はどうあれ、少年の日を追憶した作であろう。
芸人や役者を引きつれて、なじみのすし屋や小料理屋を片っぱしから飲み歩いて、一銭も勘定を払わなかった。それが何年も続き、しまいには鼻っつまみになっている。親友の水上滝太郎が見かねて、一軒一軒払って歩き、その勘定がきを、万太郎に突きつけて意見した……ちょっとした人情劇の一場面……それでもかれは一向に改めなかったという。
名作「末枯(うらがれ)」に託して、そのことをかいている。この小説の主人公は浅草の芸人たちに入れあげて落魄す
る商家の旦那となっている。
神田川祭の中をながれけり
万太郎の名句の一つ。神田川もずっと下手の柳橋にちかい神社の祭りである。神田川も昔日の姿はない。だが、かつて万太郎が住んだ、田原町、駒形あるいは三筋町界隈から、観音の境内にかけて歩くのを、ぼくが好むのは、どこかここの詩人の息吹きが、のこっているように思われてならないからである。浅草……ぼくら老書生には忘れがたい町である。(作家)
【作家・志摩芳次郎】
※作品の転載を固く禁じます。