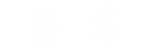以前に比べて物覚えはめっきり悪くなった。それでも懲りずにいい作品に出逢うと、一人でも多くの方々に聞いて貰いたくなり、台本作りに取りかかる。
前回記した「応援歌」、若竹千佐子作「おらおらでひとりいぐも」に続き、又、又、わくわくする作品に出会ってしまった。
葉室麟作「津軽双花」である。
私より10歳若い作家だが、残念ながら昨年暮に亡くなっている。北九州小倉の生まれで、大学卒業後は地方紙の記者や、フリーライターをしながら執筆を続け、平成16年「乾山晩愁」で作家デビューしている。それから7年後の平成23年「蜩(ひぐらし)の記」で直木賞を受賞、主に歴史小説を得意としているようだ。
「津軽双花」は、平成27年9月20日から、毎日新聞夕刊に掲載された長編小説である。単行本の表紙には、白百合と紅椿の打掛けを纏った、二人の美しい女人が描かれている。物語の主人公、「辰姫」と「満天(まて)姫」、これぞ「津軽双花」、津軽藩二代藩主、津軽信枚の正室である。
二人の正室?、理由はこうである。
秀吉の正室ねねは、夫亡き後高台院と名を改め、その菩提を弔いながら京の高台寺で静かに余生を送っていた。
関ヶ原の戦いで敗軍の将となった、石田三成の娘「辰姫」を養女とし、津軽信枚の許に嫁がせている。二人の仲は睦まじく、高台院も遠い京の空の下で、折り折りに届く便りを楽しみに暮していた。
時代は徳川の世となり、ここで登場してくるのが天海僧正、家康の知恵袋、懐刀として君臨し、三代家光の時代までその力を発揮していたと言われている天台宗の僧侶である。この天海が家康に耳打ちし、養女である「満天姫」を、津軽信枚の正室として送り込んだのが、慶長18年6月の事であった。
満天姫は、家康の異父弟下総国関宿藩四万石、松平康元の娘である。そして、十一歳の時、安芸五十万石の大名、福島正則の養嗣子、正之の許に嫁し、十八歳で嫡男直秀を生んでいる。だがその後、正則は実子忠勝の誕生で正之を廃嫡し、満天姫は直秀を伴って実家へ戻っていた。その満天姫を養女として迎え入れ、津軽家に再嫁させたのである。
いずれ大阪を攻めなければと思っている家康の心に、僅かな不安があるとすれば、仙台の伊達政宗の動きであった。その見張り役が務まるのは、津軽信枚だと天海に進言され、満天姫に白羽の矢が……。
晴天に霹靂を聞く思いで、先の正室辰姫は夫・信枚からこの話を聞かされた。
「そなたと別れるようなことは、天地神明に誓ってせぬ」
信枚のひと言を信じ、運命を受け入れながら、辰姫は津軽を去って上野国大舘の陣屋へと移って行った。
関ヶ原の合戦で、津軽家初代藩主為信は、東軍として参戦し、家康の本陣近くには津軽家の卍の幟が翻った。この功により、本領の四万五千石に加え、上州大舘二千石が飛び地として加増されたのである。
辰姫は慶長三年、七歳の時に北政所の養女となった。豊臣の為に生涯を賭けた父、石田三成の娘としての衿持を失うまい。大舘の陣屋に移ってからも、正室としての誇りを持ち続け、家臣からも大舘御前として慕われていた。高台院の養女として嫁いだ辰姫は、豊臣方石田三成の娘、家康の養女として乗り込んだ満天姫は徳川方、正に女人関ヶ原を彷彿させるが、女同志の醜い争いが一切無いのが何んとも心地良い。
祝言の夜、寝所に入った満天姫は
「いささか、お願いの儀がございます。大舘御前を召し放っていただきたいのでございます」
「あいすまぬが、わたしにはそれは出来ぬ。わたしはあの者と共に生きて参ろうと申した。わたしは一度、口にしたことは変えぬ」
「ご無礼いたしました。只今、殿が申されたことは、妻としては悲しゅうございますが、女子(おなご) としては嬉しゅうございます」
なんと、格好のいい!私は震えた。この後の展開が、又、面白いのだ。
「それでは、辰姫のことは許してくれるのか」
「それとこれとは別のことでございます。私は殿の妻でありたいと、たった今心に定めました」
満天姫は、家康の養女であると云う事を楯にせず、ひとりの女子として辰姫をしのぎたいと信枚にきっぱりと告げ
「祝言は挙げました。なれど今宵から寝所は別にしていただきたく存じます」
女は望まれてこそ、夫と共に生きていける、自分は殿に望まれる女子となる道を歩もうと思う。憎んだり恨んだり妬んだりするのではなく、殿に望まれる女となる為に自分磨きをしようと言うのである。胸がスカーッとし、そこに凜とした佇まいの満天姫が美しく描き出される。何んとも格好がいい。
やがて辰姫が身籠り、元和五年大舘の陣屋で男児を産んだ。その知らせは満天姫の耳にも届いたが、信枚と閏を共にしないと言い出した時から、このような日が来る事は覚悟していた。だが、女としての悔しさは又、別のことである。心中は複雑だった。
女の倖せは、子を持つ事である。母となった辰姫は、自らの中に母としての強さが加わったことを感じながら、子を守る事に専一し、穏やかな日々を送るのである。辰姫が産んだ子は平蔵と名付けられ、すくすくと成長していたが、やがて辰姫が病床に臥すことが多くなっていた。藩医は労咳だと告げ、今年の夏は越せないだろうと云う。
桜の頃であった。ひとりの女人が辰姫の病床を見舞っていた。満天姫である。開け放した障子の間から桜の花びらが舞い込んで来る。誠に美しい描写である。
「津軽の花は、見事に咲いたようじゃな」
石田の血を残すべく、心を砕いた高台院のことばが胸を突く。辰姫はこの年、元和九年七月二十五日に亡くなった。享年三十二だった。
五歳になっていた平蔵を、江戸藩邸に引き取り、満天姫は津軽家嫡男として立派に育てたのである。
「お吟さま」に次ぐ2時間の大作、大きな課題となった。