
東洋興業会長(浅草フランス座演芸場東洋館) 松倉久幸さんの浅草六区芸能伝<第6回>「東八郎(あずまはちろう)」
前回は少し目線を変えて、新宿フランス座で活躍した芸人たちの物語を紹介しましたが、今月号からはまたホームグラウンド・浅草フランス座に舞台を戻し、お話を進めてまいりましょう。今回の主人公は、お茶の間にたくさんの笑顔を届け、老若男女に愛された昭和を代表するコメディアン、東八郎(あづまはちろう)。自身の活躍はもちろんのこと、面倒見がよく優しい人柄で芸人仲間にも慕われた彼は、後進の育成にも力を注ぎ、お笑い文化の発展に尽くした功労者でもありました。
この地に生まれ育った生え抜きの浅草芸人は、その舞台さながらのバラエティに富んだ52年の人生を、どんな風に駆け抜けたのでしょうか…?
東八郎(本名・飛田義一)は昭和11年浅草の生まれ。父親はうちの小屋で警備員をしていたのですが、ある時、息子がコメディアンを志しているので一度会ってはいただけないかと、父・宇七のところへ連れてきたのです。まだ中学校を出て数年のあどけない少年でしたが、父は彼をひと目見た途端、この子は将来有望だと、ピンときたそうです。そこでわが社名「東洋興業」から一字をとって“東”、当時父が脚本を書く時に使っていたペンネーム「柳田七郎」に一を足して“八郎”と命名されました。このいきさつからも、彼がいかに期待されていたかが、伺い知れますね。
考えてみれば、まだどこの劇団にも所属した経験がなく何色にも染まっていない、しかも地元出身の少年を一から育て上げるという試みは、初めてのことでもありました。昭和30年、大型新人・東八郎の誕生です。
順風満帆な滑り出しを見せた東のコメディアン人生ですが、いくら社長のお墨付きといえども、ひとたびスタートラインに立てば、修行の厳しさは皆同じ。彼もまた、先輩たちが血のにじむような努力と辛抱を重ねて通ってきた道を、一歩一歩、地道に踏みしめてゆきましたが、とても素直で根が真面目な性格ですから、周囲からも可愛がられましてね、多くのよき出会いにも恵まれ、ぐんぐんと伸びてゆきました。
天性の素質に加え、東にはもうひとつ、強力な強みがありました。それは、なんといってもこの浅草に生まれ、日本一の歓楽街の空気を肌で感じながら成長したことです。オペラも映画も喜劇もストリップも飲み屋街も吉原も、日常の風景に分け隔てなく溶け込み、何の不思議もなく存在していた…そんな中で育った彼のポケットには、幼いころから知らず知らずに拾い集めた笑いのエッセンスが、ぎゅうっと詰まっていたのでしょうね。
彼が生まれ育った頃の浅草六区興行街について、ここですこし触れておきましょう。
戦前の六区は、国内外の良質な映画、大正時代から昭和初期にかけて一世を風靡した浅草オペラ、そののちに登場したエノケン(榎本健一)・ロッパ(古川緑波)らによるアチャラカと呼ばれた軽演劇などによって、大変な賑わいを見せていました。
昭和20年の東京大空襲で一時焼け野原となりましたが、戦後は奇蹟的なスピードで復興を遂げ、浅草エンターテイメントの底力を見せつけたのです。昭和20年代から30年代前半にかけては雨後の竹の子のごとく新たな娯楽施設が次々と誕生し、最盛期には実に36にも及ぶ映画館・劇場が軒を連ねました。街全体がまるで満員電車、通りを一つ渡るにも人をかき分けねばならなかったなんて、今の浅草からはちょっと想像できないでしょう?私は82歳の現在でも張りのある大きな声を褒められますが、これも若かりし日、あの人波に揉まれながら呼び込み合戦に精を出した賜物と思われます(笑)。
六区のシンボル的な存在だった瓢箪(ひょうたん)池の周囲は、ちょうど現在のホッピー通りのように小さな飲み屋で埋め尽くされ、映画や芝居がハネたあとに粕取り焼酎で一杯やろうという人々や、さてこれから隣の吉原へ繰り出すぞという連中で深夜過ぎまでごった返し…とにもかくにも当時の浅草六区興行街は栄華を極め、一瞬たりとも静まることを知らない街だったのです。
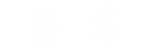






![[新企画]深見千三郎篇|活弁士『麻生子八咫(あそう こやた)』が語る!【第1回】月刊浅草オーディオブック](https://i0.wp.com/gekkan-asakusa.com/wp-content/uploads/2021/12/%E6%9C%88%E5%88%8A%E6%B5%85%E8%8D%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%95%E3%82%99_%E3%83%8F%E3%82%99%E3%83%8A%E3%83%BC.006.jpeg?resize=150%2C150&ssl=1)




