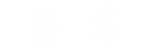東洋興業会長(浅草フランス座演芸場東洋館・浅草演芸ホール) 松倉久幸さんの浅草六区芸能伝<第2回>「渥美清(あつみきよし)」
今回は、浅草フランス座から飛び立ち、日本を代表する名優といわれるまでに上りつめた渥美清の物語をお話いたしましょう。
その前に、私自身のことも、少々。
昭和25年、長野県上田市の中学校を卒業した私は、父の仕事を手伝うために上京しました。当時はロック座の全盛期。劇場の仕事とともに、近くで母が経営する喫茶店の手伝いも掛け持ちし、朝から晩までよく働いたものです。ロック座の楽屋への出入りも日常でしたから、踊り子のお姉さん達の裸など見慣れたものですが(笑)、当時の私はまだまだ子供。女の人よりも野球の大好きな、素朴な少年でした。そんな私に、自身も無類の野球好きだった父は、
「それほど野球が好きなら、高校へ行ってみたらどうだ。野球の盛んな学校へ入って、頑張ってみるといい。」
と言ってくれたのです。こうして、1年遅れにはなりましたが、翌春私は晴れて高校へ入学しました。当時都内一といわれた野球の強豪校、日大三高です。
もっとも、学校から帰れば以前と変わらず家業の手伝いに力を注いでいましたから、寝る間もないほどの超多忙な日々でしたが、色々な意味で私の基礎は、間違いなくこの時代に築かれたのだと思います。大変といえば、確かに大変。でも、こんな風変りでエキサイティングな青春時代、そうそう経験できるものではありません(笑)。なんて貴重な宝物だったことでしょう!
15歳から82歳の今日に至るまで実に60余年に及ぶ私の浅草六区興業史は、こんな風にして幕を開けたのでした。
渥美清のことは、強烈な印象として記憶に残っています。出逢いは私が高校を卒業していよいよ本格的に仕事に取組み始めた頃でしたが、彼は舞台に立ち始めた当初から頭角を現し、見る者全てを圧倒してしまうような底知れぬ魅力を持ったコメディアンでした。
渥美清、本名・田所康雄は昭和3年、上野車坂(現在の台東区上野7丁目)に、新聞記者の父、代用教員の母の次男として生まれました。経歴については謎の部分も多いのですが、20代前半には、生きるがためアメ横や浅草寺の境内あたりでテキ屋みたいなことをしていたらしい。そう、後に生涯の当たり役となる「寅さん」を地で行くような時代が、実際にあったようなんですね。けれどテキ屋稼業はお天気次第、雨が降っちゃぁ仕事にならねぇ。そうだ、役者なら雨が降ろうが槍が降ろうが食ってけるんじゃねぇか…なんてことを考えたかどうかはわかりませんが(笑)、いつからかコメディアンを志し、浅草の百万弗劇場に出ていたところをうちの文芸部員に見い出され、スカウトという形で昭和28年、フランス座の専属となったのです。
当時のフランス座は開場2年目にして益々の大盛況、専属コメディアンも10人以上はいました。初代座長は、後に由利徹、南利明と「脱線トリオ」を組み一世を風靡した八波むと志。他の追随を許さぬ勢いのある役者でしたが、そこは人気者の宿命、やがてTV業界へと引き抜かれてゆきました。その頃うちの小屋では佐山俊二、谷幹一、関敬六などの才気溢れる面々がしのぎを削っていたのですが、そんな中、渥美は彼らをたちまち追い越し、2代目座長に収まりました。そうなるだけの天賦の才と輝きが、やはり彼にはあったのですね。その上テキ屋時代に磨きをかけた話術でお客さんの心をがっちり掴んで離さないのだから、そりゃもう怖いものなしです。ひとたび彼が板に上がれば、踊り子や裏方たちまで一斉に集まってきて、舞台袖で見学しながらお客さん同様に笑い転げていたものですよ。
けれど渥美の役者としての魅力は、危うさと隣り合わせでもありました。荒っぽくてね、あちこちで喧嘩はするわ、若いコメディアンをぶっ飛ばすわ、あげくに舞台の上からお客さんともやり合う始末。“お前の演技は下手だなぁ!”なんてヤジが飛ぶと、“バカ野郎!入場料返してやるから、とっとと帰りやがれ!”なんてね。もっとも、こんなやり合いは芸の一つのようでもあり、観客たちは大喜びしていましたが(笑)。
しかしこれほどの暴れん坊だった彼が、ある出来事をきっかけに、まるで別人のように変わってしまったのです。